| 骨折低減のための骨粗鬆症リエゾンサービス |


|
| 【骨粗鬆症リエゾンサービスは骨折低減のための多職種での取り組み】 |
|
日本骨粗鬆症学会は、骨粗鬆症の知識をもった医療専門職(メディカルスタッフ)を骨粗鬆症マネージャーとして教育・養成し、医師とともに骨粗鬆症性骨折の1次予防、2次予防を効果的に推進する取り組みとして、骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS:Osteoporosis Liaison Service)を開始している。 骨粗鬆症の予防や治療は、医師だけの力では十分にできないことが多い。薬物治療、運動療法、栄養改善などに関する患者への説明や教育、必要な治療の継続などについて、それぞれの職種の特徴を活かして全体として骨折予防を推進していくことにより、わが国の骨折を減らしていくシステムがOLSである。 |
| 【骨粗鬆症リエゾンサービスはイギリス発症で世界に広がっている】 |
|
わが国の骨粗鬆症人口は1280万人と推計されているが 1)、わが国の高齢化は今後も進行するため、骨粗鬆症患者数も増え続けると予想される。それと同時に高齢者の脆弱性骨折も増加すると考えられる。骨粗鬆症治療薬は、現在ではビスホスホネート、SERM、テリパラチド、デノスマブなどが中心であり、これらの薬剤は大規模臨床試験で骨折予防効果が証明されている。ところが、骨粗鬆症患者のうち20~30%しか実際に治療を受けておらず、骨折が増加するもうひとつの要因と考えられている。脆弱性骨折を起こした後でさえ、治療率は低く、骨折の1次予防も2次予防も不十分な状態である 2)~5)。 海外でも同様で、イギリスでは1992年に大腿骨近位部骨折患者の追跡調査を多施設で行ったところ、多くの患者が追跡不能であり、骨折後の骨粗鬆症治療がかなり不十分であることが明らかとなり、これを機にFracture Liaison Service(骨折リエゾンサービス)が始まった。これは、骨折患者をリスト管理し、再骨折を予防、つまり二次予防を医師とともに他の医療専門職の協力も得て確実に実施する取り組みである。特に、リエゾンナースと呼ばれる看護師が骨折患者のリスト管理やかかりつけ医への連携などの役割を果たし、理学療法士や薬剤師なども協力して、多職種で骨粗鬆症治療、転倒予防を図った。 Glasgow大学の関連病院を中心として行われたFLSでは、1999年から10年間で約5万例の骨粗鬆症性骨折患者が登録された結果、英国全体では大腿骨近位部骨折が17%増加したが、FLSを実施した地域では、同骨折が7.3%減少した 6)。その後、FLSは欧米各国に広がり、オランダで行われた介入試験では、非椎体骨折後の患者にビスホスホネート剤を服用することを徹底したことで、24ヶ月間の観察期間で非椎体骨折の発生が56%、死亡率が35%低下したと報告された。 7) こうした海外でのFLSの有効性を背景に、わが国では骨折の二次予防だけでなく、一次予防も含めた多職種による骨粗鬆症の治療率の向上や転倒予防を目的とした取り組み「骨粗鬆症リエゾンサービス(Osteoporosis Liaison Service: OLS)」の準備が始まった。 |
| 【骨粗鬆症マネージャー制度はレクチャーコースと認定試験】 |
|
日本骨粗鬆症学会では、2011年度に骨粗鬆症リエゾンサービス委員会(OLS委員会)およびメディカルスタッフ認定事業委員会(認定事業委員会)を創設した。OLS委員会が骨粗鬆症マネージャー養成のためのレクチャーコースを実施し、認定事業委員会が試験を行い認定する。2012年10月から2014年10月までに5回のレクチャーコースが開催され、2014年11月には最初の骨粗鬆症マネージャー認定試験が開催された結果、2015年4月から約700名の骨粗鬆症マネージャーが誕生した。 レクチャーコースは年2回(3月、および9月または10月)開催される4時間ほどのプログラムで、骨粗鬆症の疫学、診断、治療から、骨粗鬆症マネージャーの役割まで内容は多岐にわたっている。骨粗鬆症マネージャーの資格認定要件は、(1)医療に関わる国家資格を持っている、(2)レクチャーコースを受講している、(4)日本骨粗鬆症学会の会員である、(4)認定試験に合格している、の4項目である。受講者は、看護師、理学療法士、薬剤師、管理栄養士が多い。 |
| 【骨粗鬆症リエゾンサービスの取り組みは病院、診療所、地域で異なる】 |
|
骨粗鬆症リエゾンサービスの具体的な活動は、病院、医院・診療所、施設、地域・社会などによって異なるが、目標は骨粗鬆症の治療率向上と治療継続率の向上による骨折の防止である。 病院でのOLS介入は、海外のFLSと同様に、骨折の二次予防を効果的に実施することが必要である。大腿骨近位部骨折や脊椎椎体骨折患者をはじめとして、他の骨粗鬆症性骨折も含めて対象患者を決め、確実なリスト管理を行った上で二次予防に必要な薬物治療を行い、運動や栄養の重要性や具体策を指導する。骨折患者は骨折のハイリスク状態にあるため、多因子的なアプローチを十分に行うことが必要で、特に骨粗鬆症薬による治療が退院先によらず継続されるようにする。 病院や診療所の外来患者に対しては、骨粗鬆症患者への疾患や骨折予防に関する説明(説明資材の活用を含む)や骨粗鬆症薬の作用・副作用の説明を十分に行うことにより、確実な服薬継続を勧める。外来や診療所では患者数が多い一方で、関われるメディカルスタッフは限られている。医療機関内では看護師が中心となり、病院での薬剤部や調剤薬局で薬剤師の役割が重要であると考えられる。 施設では、看護師や薬剤師、介護福祉士、理学療法士などが中心的な役割を果たす。高齢者施設では、入所者に骨粗鬆症患者が多いこと、転倒リスクの高い者が多いことから骨折の発生が多い。特に日光にあたる機会が少ないため、活性型ビタミンDやビスホスホネート剤の投与を積極的に考慮する。骨粗鬆症薬の継続とともに、転倒予防のための運動を日々行うことも重要である。 地域においては、一般住民に対しての骨粗鬆症に関する普及啓発が重要である。自治体、医療機関、医師会、企業などが主催する講演会は骨折の1次予防に重要であり、骨粗鬆症マネージャー資格を持つ保健師・看護師や理学療法士、作業療法士、介護福祉士などが関与できると、より効果的な講演会運営が可能となると思われる。 |
| 【伊奈病院骨粗鬆症リエゾンサービス委員会の組織とその取り組み】 |
|
筆者の勤務する伊奈病院では、2014年6月から骨粗鬆症リエゾンサービス委員会(OLS委員会)を創設した。多職種によるOLSチームを作ることをまず考えたが、任意の集まりでは継続が難しいと考えられたため、院長や事務長、看護部長の了解を得て、委員会として活動を開始することにした。メンバーは、医師(整形外科医、つまり筆者)、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、そして国家資格保持者ではないが、病診連携室担当者と診療秘書課担当者である(表1)。月に1回の委員会を開催し、全員で集まって院内の取り組みなどを話し合う。委員会として、現在取り組んでいる、あるいは今後予定していることは以下の通りである。(表2) 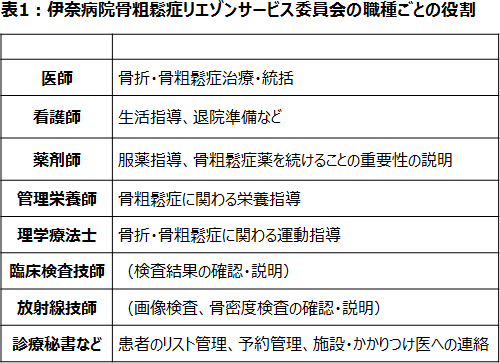 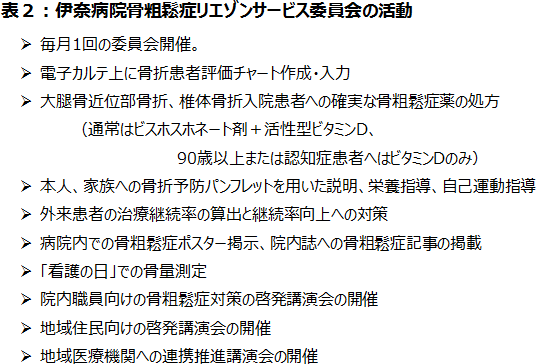
退院が近づくと、各メディカルスタッフからの指導を行なう。看護師は、退院後の生活指導、退院後の施設入所や自宅退院時の在宅介護の準備などを、診療秘書、ケースワーカー、地域のケアマネージャーなどと連携して行う。薬剤師は骨粗鬆症薬が確実に処方されているかの確認をして、処方されていない場合は医師へ処方を促す。処方内容は、活性型ビタミンDとビスホスホネートが中心である。ただ、90歳と超えた患者、認知症のある患者は服薬管理が難しいことが予想されるため活性型ビタミンDのみとしている。さらに、患者または家族に対して骨粗鬆症治療薬の内容説明や継続の重要性について説明する。管理栄養士は自宅退院予定の患者に対して骨粗鬆症や骨折予防のための栄養素の摂取などについて説明する。理学療法士は、退院後の自己運動メニューなどを作成し指導し、同時に継続的な運動の必要性への理解を促す。これらの指導は、骨粗鬆症や骨折に関する独自に作成した説明パンフレット「強く良い骨を作るために」(図3)を用いて行っている。 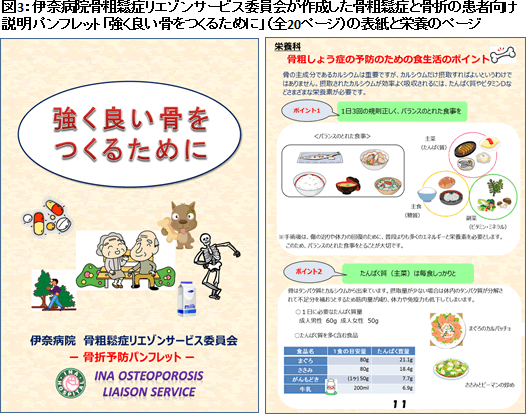
上記以外の取り組みとして、外来待合いスペースでの「骨粗鬆症リエゾンサービス」広報掲示板、患者向け院内誌「ハーモニー」での「骨粗鬆症リエゾンサービス」連載ページ、看護部主催で行われる「看護の日」地域住民向けイベントでの骨量測定、院内での他の職員に向けた講演会、地域住民向けの骨粗鬆症と骨折に関する講演会の開催、地域の他の医療機関、医師、多職種に向けた連携促進のための講演会などを企画している。 【文献】
※お客様の使用経験に基づく記載です。仕様値として保証するものではありません。 資料請求などのお問い合わせがございましたらこちらまで |
 まず、大腿骨近位部骨折と脊椎椎体骨折の入院患者のリスト管理と介入である。該当患者が入院すると診療秘書課担当者が電子カルテ上に作成した骨粗鬆症リエゾン評価リストに登録する。登録内容は、基本属性、既往症および既存合併症の確認、骨折の部位やタイプ、手術などの治療内容、X線による椎体骨折の数や程度、リハビリテーションの進行、入院中の合併症、入院期間などを記録する。入院後(または手術後)概ね2週経過後にDXA(GE社PRODIGY)による骨密度測定を行う。これは、現状をできるだけ正確に把握し、事後の解析に役立てることに加えて、退院後の経過観察の際に骨密度の治療による改善が目に見える形になる方が患者の治療継続につながるとの利点を考慮したためである。
まず、大腿骨近位部骨折と脊椎椎体骨折の入院患者のリスト管理と介入である。該当患者が入院すると診療秘書課担当者が電子カルテ上に作成した骨粗鬆症リエゾン評価リストに登録する。登録内容は、基本属性、既往症および既存合併症の確認、骨折の部位やタイプ、手術などの治療内容、X線による椎体骨折の数や程度、リハビリテーションの進行、入院中の合併症、入院期間などを記録する。入院後(または手術後)概ね2週経過後にDXA(GE社PRODIGY)による骨密度測定を行う。これは、現状をできるだけ正確に把握し、事後の解析に役立てることに加えて、退院後の経過観察の際に骨密度の治療による改善が目に見える形になる方が患者の治療継続につながるとの利点を考慮したためである。