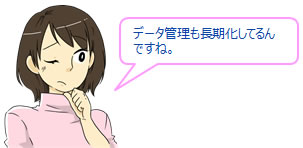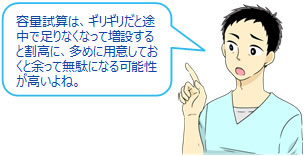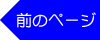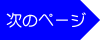第七話 外部保存の注意点とは?[Page 2/4]
今回のキーワード:安全性、中立性、第三者認証、PDCAサイクル、ISMS、VNA
| 志位: | 「なるほど、面白そうだね。喜んで参加させてもらうよ。」
|
| イチロー: | 「ありがとうございます。では最初に、外部保存サービスを採用するにあたって大事なことは何か、について教えていただけますか?」
|
| 志位: | 「うん。これは外部保存に限った話ではないけど、『目的』を明確にすることだね。外部保存というのは、何らかの目的を達成するための『手段』であって、外部保存をすること自体が『目的』になってしまってはいけないよね。」
|
| くらら: | 「目的というのは、例えば、災害からデータを守る、とか、そういうことでしょうか?」
|
| 志位: | 「そう、もちろん災害対策が目的のこともあるね。当院では、医用画像のデジタル化への取り組みは比較的早かったから、1995年あたりからすでに20年分のデジタル画像データが保管されているんだ。これらは患者さんにとって貴重な記録であることはもちろん、臨床や研究の観点から我々にとっても非常に重要な資産だよね。東日本大震災の経験から学んだことと、これからも南海トラフに代表されるように大規模震災はいつか確実に来ると言われているから、しっかりと対策をとっておきたいと考えているんだ。それに加えて、当院の場合には、サーバ室の設置スペースの削減が必要な状況なのと、長期的なデータの維持・管理を専業ベンダーに任せることで、データの保全とセキュリティの向上を図りたい、などといった複合的な目的があるんだよ。」
|
| イチロー: | 「災害対策や設置スペースのことはメリットの説明の中で教えたよね?」
|
| くらら: | 「はい。でも、うちの設置スペースって、そんなに逼迫しているんですか?」
|
| 志位: | 「うん、当院は急性期の地域中核病院で、がん診療にも力を入れているよね。がんは治らない病気ではなくなりつつあるから、慢性化によって疾病管理も長期化しているんだ。すると当然、診療に用いられたデータも長期的な保存が求められるんだけど、次の更新の時には、すべてのデータを院内に持とうとすると、既存のサーバ室のスペースでは足りないことがわかったんだ。サーバ室を増やすには、まず部屋の確保、フリーアクセス床の設置、空調設備の増強、電源容量の増強、入退室管理用セキュリティシステムの設置など、かなりのコストがかかるんだよ。そこで、外部保存サービスを利用することで、院内スペースの有効利用を図りつつ、コストも抑制することにしたんだ。」
|
| くらら: | 「データ管理も長期化してるんですね。」
|
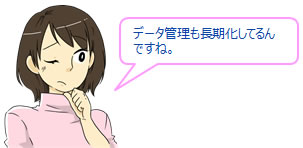 |
| 志位: |
「そう。しかも、特に画像データの発生量の伸びは著しくて、ここ数年は年率15%以上伸びている。増加率が15%だと、5年おきにデータ発生量は約2倍になっていくんだよ。蓄積量としては5年で3倍、15年だと15倍にもなるんだ。それに対して、ハードディスクの容量単価は、ここ数年、横ばいになってるんだ。システム更新にかけられる予算は増やせない中で、自前で保管し続けるのは非常に苦しくなってるんだよ。」 |
|
| イチロー: |
「当院の場合は、かなり正確な容量試算が出来ているけど、それでもギリギリの容量を用意して、途中で足りなくなって増設すると割高になるし、前もって多めに用意しておくと余らせてしまって無駄になる可能性が高いよね。」
|
| くらら: |
「外部保存サービスなら、月々使った容量の分だけ負担すれば良いから無駄がないってことですね?」
|
|
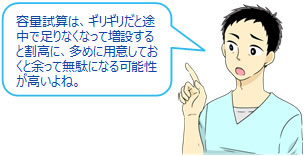 |
| イチロー: | 「そうだね。ところで先生、外部保存を考える時に、一番注意すべきことは何でしょうか?」
|
| 志位: | 「そうだねえ、私の立場から言わせてもらうと、大きく2つあるね。ひとつは『安全性』、もうひとつは『中立性』かな。」
|
| くらら: | 「安全性と中立性ですか。まず安全性については、具体的にはどのような注意が必要でしょうか?」
|
| 志位: | 「うん。外部保存が委託サービスだってことはもう聞いたかな?委託ってことは、委ねて託すということだよね。病院として義務を負っている『診療情報の保管』を、外部、すなわち民間の事業者に委ねるってことなんだ。だから、 受託する事業者には、我々がデータ保管に関して義務を負っている、セキュリティの担保などの責任をきちんと果たしてもらわなければならないんだ。」
|