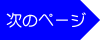第三話 「外部保存」とPACSの関係����
��#2 PACSのストレージ構���� [Page 1/3]
今回のキーワード: ストレージ、SSD、RAID、STS��LTA、検像、確��
| くらら�� | 「蔵田先輩��前回��DICOMのことを教えてくださって、ありがと����ざいました���� |
| イチロー�� | 「市野さんが勉強熱����から、僕も教えが����あって嬉し����。�� |
| くらら�� | 「今回はPACSのストレージにつ����ですよね���� |
| イチロー�� | 「そ����ね。外部保存につ����、より良����討をするためにも、PACSの���タ保管方法につ������ 正しく����しておくべきだと思うんだ。�� |
| くらら�� | 「ストレージと����のはハ��ドディスクのことですよね�� �� |
| イチロー�� | 「うん、今��ハ��ドディスクが主流だね。でも��ストレージと����のは���タ記������全般を意味するので�� ハ��ドディスクに限定されるわけではな��んだ。��は、������スクやMOなどがあったし、今で��CD、DVD�� 磁気テープ、Blu-rayなどが使われて����。これから��SSDのようなフラ����ュメモリ型��ストレージも使われ るケースが増えて����と思うよ。�� |
| くらら�� | 「エスエス����ーって何ですか���� |
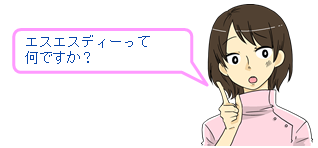 |
|
| イチロー�� | 「Solid State Driveの略で、フラ����ュメモリーを使ったストレージ媒体なんだ��ハ��ドディスクは������ 回転して����ので常時電力を使����ど、SSDはアクセスされた時しか大きな電力を使わな���で消費 電力や発熱量も抑えられる��現状ではま��高価��けど��読み書き��スピ��ドがハ��ドディスクより速い�� ら、次世代のストレージとして注目されてるん��。�� |
| くらら�� | 「うちの����のPACSでは、どんなストレージを使って����んですか���� |
| イチロー�� | 「うちはRAID6のハ��ドディスク��よ。RAIDにつ����は知ってるかな���� |
| くらら�� | 「レイド?�� |
| イチロー�� | |
 「うん、RAIDって����のは、”Redundant Array of Independent(Inexpensive) Disks”��略で、����のハ��ドディスクを����合わせて、あたかも��とつの大きなハ��ドディスクのように見せて、読み書き��スピ��ドを向上させたり、故障からデータを守ったりする技術なんだ。RAIDには0��1��5��6などの種類があるけど��PACSの画像データを保存するストレージには、主にRAID5かRAID6が使われる��どちらもハ��ドディスクが壊れた時に、壊れたハードディスクを交換すれ��そこに入って�������タを修復する機��があるん��よ�� RAID6の場合には同時に2つのハ��ドディスクが壊れても修復が可能なんだ。�� |
|
| くらら�� | ��3つ同時に壊れることはあり得るんですか���� |
| イチロー�� | 「確���低いけど、絶対にな����は言えな���。�� |
| くらら�� | 「もし起こったら、ど����るんですか���� |
| イチロー�� | ��最悪の場合、そこに入って�������タは二度と見られなくなる可能性があ��よ。�� |
| くらら�� | ��患����ん��診療データは����子保存��3原則で、しっかりと守らなければならな����ですよね���� |
| イチロー�� | 「そ����第1��で教えたよね����から、PACSでは、データを二重化して管����て����んだ���� |
| くらら�� | 「RAIDとは別に、二重化して����ってことですか���� |
| イチロー�� | 「そ����よ。PACSが受信した���タは、まず短期ストレージと呼ばれる場所に格納されて、一定時間が経過したのちに長期アーカイブと呼ばれる場所にもコピ��されて二重化されて����んだ��短期ストレージのことをShort Term Storage、略してSTSとも言������長期アーカイブ��Long Term Archive、略してLTAと言ったりもするよ。�� |