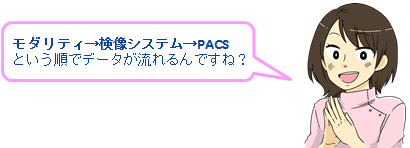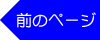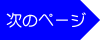第三話 「外部保存」とPACSの関係����
��#2 PACSのストレージ構����
[Page 2/3]
今回のキーワード: ストレージ、SSD、RAID、STS��LTA、検像、確��
| くらら�� |
「エス����ーエスとエル����ーエーですか。どちらもハ��ドディスク、すなわちRAIDなんですか����
|
| イチロー�� |
「��はハ��ドディスクが高かったから、LTAにはCDとかDVDとかテープを使����とが多かったん��。た��、こ����たメ����アは���タの読み書きにすごく時間がかかる��が��点なので、今��STS、LTA共にハ��ドディスクを使����とが多くなって����ね。��
|
| くらら�� |
「うちのPACSはど����んでしょ������
|
| イチロー�� |
「前回更新した時から両方ともRAIDになって����よ。さて、話を戻して、画像データの保管の流れをおさら����てみよう。前回話したように、画像データはモダリ����から発生するよね。前回��復習だけど、次にど����るん��っけ?��
|
| くらら�� |
「えーと、DICOM通信で、主に非圧縮でPACSに送信されて、PACSは受信した���タを可����縮して 保存する、でしたっけ?��
|
| イチロー�� |
「そ����その通り��よく覚えて����ね。た��し��フィル��レス運用の特徴として、モダリ����とPACSの送受信の間に『検像』と����行為があるから覚えておいてね。�� |
| くらら�� |
「あ、一般撮影ゾーンでベテランの方がやってらっしゃ����すよね。あれが検像ですよね���� |
| イチロー�� |
「そ����������師が撮影した画像が、診断に用����のに適������������質になって����かチェ����して、����に応じて修正するのが『検像』だね。��
|
| くらら�� |
「じ����、モダリ����→検像シス����→PACS、と�����������タが流れるんです������
|
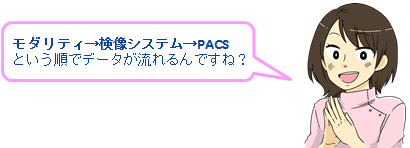 |
| イチロー�� |
「当院ではそ��流れ��ね。た����検像のためのシス����が����なければならな����と����ことではな���� ��。モダリ����のコンソール上で十��にチェ����して直接PACSに送信する場合もある。病院ごと����検査�� とに運用ルールを決めて構わな����大事なのは、正しくて診断に適した画像を適����タイミングで提供す�� こと��からね。�� |
| くらら�� |
「������わかりました��PACSに入った後��STSからLTAにコピ��して二重化されるんですよね。��
|
| イチロー�� |
「そ����ね。でも、いつコピ��されるか知ってるかな����
|
| くらら�� |
「え��いつって言われても・����、わかりません、教えてください����
|
| イチロー�� |
「うちの����では、STSに入った後��『確定』されてはじめてLTAにコピ��され��んだよ。�� |
| くらら�� |
「かくて������ |
| イチロー�� |
「そ����『確定』。診��(診断)に用����原本として書き換えできな����態にすること��ね。��
|
| くらら�� |
「『検像』とは違うんですか���� |
イチロー��
|
「『検像』イコール『確定』ではな����。『検像』した後でも、ま��診断に用��������ければ修正して上書きすることは可能��からね。でも、『検像』した時点で、『確定』とする運用もあると思う。��
| くらら�� |
「『検像』と『確定』かぁ。なんか区別がしづらいです��。�� |
|
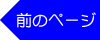
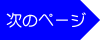
診断用の原本として画像データを確定する��は誰の仕事��